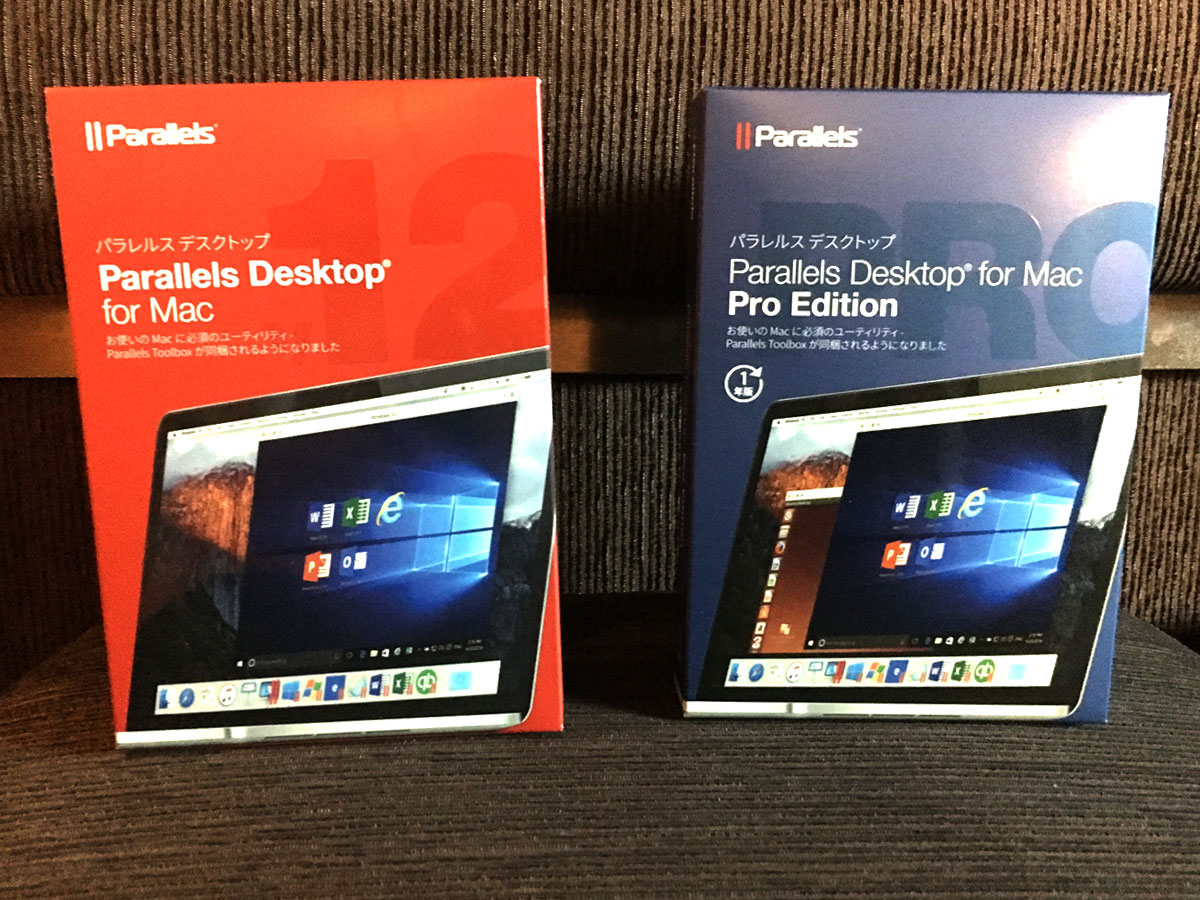箱根のポーラ美術館の企画展「ルソー、フジタ、写真家アジェのパリ――境界線への視線」プレスツアーに参加しました。本記事では、なかでももっとも印象に残ったルソーとエッフェル塔についてご紹介します。
アジェからルソーへ
のっけから唐突ですが、この企画展のお知らせをいただいたとき、わたしがもっとも興味を惹かれたのはアジェでした。企画展のタイトルに、わざわざ「写真家アジェ」と書かれるくらい、アジェの名は一般には知られていません。わたしは大学院でメディア論に近い研究をしていたため、ヴァルター・ベンヤミン『写真小史』でアジェをはじめて知りました。
アジェは19世紀のパリで、絵画のための資料写真を撮影し、売り歩いていた写真家です。でも、彼の被写体はパリの名所でもなく、有名人の肖像でもない。本来なら生活感のある卑近な場所、通りを行く無名の人々を撮りながら、どこか無機質で静謐な写真に仕上げる写真家というのが、わたしにとってのアジェ像でした。
芸術的写真家ではない、職業的写真家と言えば良いのでしょうか? しかし、アジェからは芸術的魅力を感じる。だからこそ、アジェの写真を観てみたい。わたしにとってこの企画展のメインはアジェだったのです。
しかし、実際にポーラ美術館で作品を観てみると、ルソーの絵の持つ力にすっかりやられてしまいました。ルソーの作品は、圧倒的でした。
画題としてのエッフェル塔
この企画展で観るべき絵を1枚選ぶのであれば、「エッフェル塔とトロカデロ宮殿の眺望」を挙げたいとおもいます。

(プレスツアーのため、特別に撮影を許可れています)
戦後の日本では、スポーツ同様、芸術は政治とは切り離された「クリーンなもの」として捉えられることがあります。とはいえ、artそもそもの成り立ちから、芸術は権力と権威が付随する極めて政治的な存在です。端的に言えば、芸術の担い手たる芸術家は教会や貴族といったパトロンによって養われていたからです。
ゆえに、かつての西洋画壇における絵画は、教会に飾るに相応しい宗教的モチーフであったり、貴族の肖像であったり、あるいは図象として宗教性を含む作品だったのです。そのため、19世紀当時は「芸術家」たるものの作品において、エッフェル塔は主要なテーマにはなりえませんでした。
エッフェル塔とは
いまではパリの象徴となっているエッフェル塔は、第4回パリ万国博覧会に合わせて建設されました。
1855年からはじまるパリ万国博覧会の系譜を紐解くと、1878年の第3回にはエジソンの自動車や蓄音機やベルの電話機が出品されており、それまでの生体的な時間距離を一気に短縮する、新しい世界観を提示することとなりました。パリ万国博覧会は、ひとびとに輝かしい未来の夢を見せる役割を強めていたと考えられます。
金属産業の象徴として、1889年の第4回パリ万国博覧会に合わせて建てられた、鉄骨のエッフェル塔は、フランスの産業力を内外に示すとともに、「花の都」という従来のパリがもっていたイメージと、最先端の科学を集約したイメージを一手に引き受け、庶民にとって憧れの存在であったはずです。
東京タワーやスカイツリーを見慣れたわたしたちにとっても、エッフェル塔は美しい歴史的建築物であり、パリの象徴です。フランス好きの人であれば、エッフェル塔モチーフの雑貨をひとつやふたつ、気に入って持っているはずです。
しかしながら、当時の「美意識」を持ちあわせたパリの知識人たちにとって、エッフェル塔は奇抜で醜悪な存在でした。パリ万国博に先立ち、コンペティションで選ばれたエッフェル塔の建築が決まったとき、芸術家たちのなかには、建築反対の署名運動を起こすほど、物議をかもしたようです。
ルソーとエッフェル塔
では、パリの税関吏であったアンリ・ルソーは、パリと郊外の境界で小役人として働きながら、エッフェル塔をどのような気持ちで見つめていたのでしょうか?
パリ万博には多くの庶民が足を運んでいますし、ルソーもエッフェル塔を間近で眺めた経験があるはずです。パリ市内の外から観た構図で描かれているルソーのエッフェル塔は、橋や川の向こう側に茂る森から、第2展望室より上の部分が顔を覗かせているだけです。
モデルネの絵画、ルソーの絵の特徴
さて。ここで、ポーラ美術館の木島俊介館長による挨拶のなかでなされた「謎かけ」をご紹介したいと思います。
ルソーの作品はたくさん展示ますが、ルソーの中に描かれる人物はほとんど後ろ向きに捉えられています。一体この人物は、風景を観ているひととして描いているのか、風景を観ている自分を表現したくて、後を向いている人物を風景の中に描いているのか。ここにも19世紀から20世紀の過渡期としての、境界線の謎があるという風に思います。

ルソーの絵には、画面の手前に、後ろ姿の人物が描かれています。ルソーの絵を見るとき、描かれた人物が風景を観ているというふうにとらえることも、その人物を描き手であるルソーに重ねてみることもできるし、われわれはがその人物になったつもりで絵の中に入り込むこともできる。それでは、みなさんはどのようにこの絵をご覧になりますか?
彼は絵の中に描かれた被写体であり、ルソーであり、わたしたちでもある、その境界線をたゆたうのがルソーの絵なのかもしれません。
あこがれは とおくにありて 描くもの
40歳、人生を折り返した後に独学で絵を描きはじめたルソーは、画壇の「職業芸術家」には成り得ません。そして、彼の本業である税関吏は、パリの中心から離れた、周縁に縫い止められる仕事です。
「エッフェル塔とトロカデロ宮殿の眺望」を、もう一度観てみましょう。

(プレスツアーのため、特別に撮影を許可れています)
わたしのきわめて個人的な解釈ではありますが、森の向こう側に、遠くに描かれる曖昧な描写のエッフェル塔は、ルソーにとって、月同様、手の届かない憧れなのではないかと想像します。
そもそも、右下に夕焼けがあるのに、月の左側が赤く染まっているのは、まったく不自然です。ほとんど夢のなかの月と言っていいでしょう。キャンバスの中心に並び描かれる、夢のように曖昧なエッフェル塔と月。
そうしてみると、釣り竿を右手に持ち、茫洋と橋の向こう側を眺める人物の肩が、さみしげに見えてくるのです。手の届かないものを見つめる、さみしげな後ろ姿として、この目に映るのです。
まなざすひとにとってのルソー
ここまで、大げさにルソーの青ざめた憧憬をとりあげてきましたが、実際に展示室でルソーを目の前にすれば、この気持ちがわかっていただけるかと思います。あるいは、もっと違う解釈を持つ向きもあるかもしれません。
みなさんなら、どのようにルソーを観るでしょうか? そして、館長のなぞかけに、どのような答えを出すでしょうか?
ぜひ、ポーラ美術館に足を運んで、みなさんなりのルソーを感じていただけたら、とおもいます。